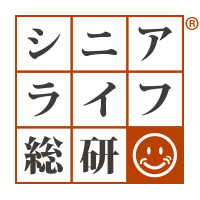第27回 アサヒシューズ株式会社
日本製への拘りと独自の販路開拓によって育成されたブランド「快歩主義」第4回
執行役員 / 営業・商品本部戦略ブランド販売部
快歩主義グループ ブランドマネージャー
穴井 政春氏
創業以来120年以上に渡って、高品質の靴を作り続けてきたアサヒシューズ株式会社。確かな技術と信頼の背景には、国内工場製造への深い拘りがありました。
そして、今シニア市場で話題の商品「快歩主義」は、健康・快適シューズ市場においてNo.1のブランド(※)に成長しています。(※2012年シューズポスト紙調べ)
今回は、この「快歩主義」ブランドの育成と販路拡大を含め、アサヒシューズのシニアマーケティングへの取り組みについて深くお話をお伺いします。
2018年5月取材

業種を超えた流通対策
【SLS】それでは、いよいよ販売と流通に関する手法について教えてください。
【穴井】まず、漫画を書いています(笑)

正確には、漫画そのものは別の社員に依頼しているのですが、設定やストーリーはすべて私が自分で考えています。
【SLS】面白いのが、街のカメラ屋さんに快歩主義の取扱いをオススメするというストーリーになっていることです。
【穴井】これ、実は異業種向けの新規開拓用営業ツールです。
今、私どもが積極的に取り組んでいるのが、異業種の小売店さんを開拓することです。靴屋さんではない全くの異業種の小売店さんに「快歩主義」を置いていただくことにチカラを入れております。
【SLS】いろいろお聞きしたいのですが、まずは最初の質問です。なぜ漫画に行き着いたのですか?
【穴井】商店街で営業を行っていると、お話を聞いてくださる店主さんやオーナーさんも、皆さんシニア層の方です。
そういう方々に、杓子定規にとりまとめられた文字ばかりの企画書をお持ちしても興味をもってもらえません。
しかも、異業種の皆さんです。そんな方にいきなり靴の取扱のお話をしても「えっ?!」と思われてしまいます。
だから、ひと目でわかりやすく、内容も入っていきやすい漫画に着目したのです。
【SLS】次に、異業種開拓へチャレンジした理由をお聞かせください。
【穴井】理由は単純です。靴屋さんだけをターゲットにしていても販路拡大には限界があるからです。
今は、いくら探しても新規の靴屋さんなどありません。言い換えればほとんどの街の靴屋さんが既に弊社のお取引先です。
そして、その靴屋さんが今、減少傾向にあります、というのは靴屋さんというのは大変な商売です。
1つの商品を売るためにおよそ5~8種類のサイズを用意しておかなければなりません。在庫というのは靴屋さんにとってそれは大きな負担です。
そういう理由もあって、街の靴屋さんは事業継承されず廃業されるケースも多く、同時に弊社の取引先も減っていきます。
だからと言って何もしないわけにいかない。年々減っていく得意先を悲しんでいても何も生まれません。だからこそ異業種開拓です。開拓先は主に商店街の店舗です。
全国的に商店街は衰退傾向ですが、実はシニアの方にとって商店街は未だ大事な存在です。シニアの行動範囲は限られています。郊外のショッピングセンターまでなかなか足を伸ばせません。
【SLS】俗に言う「買い物難民」問題ですね。
【穴井】そうです。だから私たちはもう靴屋さんに限定せず、「レジのあるところならばどこへでも提案する」という方針で開拓を進めています。
洋服屋さんは元より、電気屋さん、クリーニング屋さんなど、商店街にあるいろんな業態に靴の取扱いをオススメしています。
更には、道の駅、ガソリンスタンド、ネイルサロン、家具屋、ランジェリーショップなどにも置いてもらっています。
この漫画のモデルになっているカメラ屋さんは(広島県の)呉駅前にあるんですが、今では、店舗の半分が靴の展示スペースで占められています。
【SLS】いわば、靴を通じた、シニアの方と商店街のマッチングですね。
【穴井】これはコカ・コーラさんの「喉が乾いたらコカ・コーラ」という戦略からヒントをいただきました。いわば、「シニアがいるところには快歩主義」です。
「快歩主義」を置いてくださる店舗さんには、展示用・装飾用の什器と店頭用のノボリなどを一式でご提供しています。少しの空きスペースにこれらを置いて頂いて、シニアの皆さんとの接触ポイントを作っています。
もし、購入意思のあるお客様がいらっしゃれば、店舗内で靴(のサイズ)合わせをしていただきます。「快歩主義」のデザインは多数ありますが、ベースは同じなので(22.5~25.0までの)5サイズ分だけ店舗内に置いておいていただければ靴屋としての商売が成立します。
あとは設置したカタログからデザインを選んで頂きます。そうすれば翌日には弊社から商品をお届けすることができます。
【SLS】専門家がいなくても、試し履きが何よりの商品説明になるから、商売になるのですね。
【穴井】今は、こういう異業種店舗向けの販路開拓を行う専門チームが社内にあります。
当初は西日本が中心でしたが今は首都圏においても開拓を進めています。首都圏内においても困っている商店街や買い物難民エリアはたくさんあります。
異業種店舗で靴が売れる、その理由
【SLS】各店舗オーナーさんからはどんなお声が挙がっていますか?
【穴井】手前味噌ですが、よく売れると喜んでもらっています。
人が離れたと言っても、実は店舗さんはちゃんとお客さんをお持ちです。中には名簿や台帳を作ってお客さんをしっかり管理していらっしゃる店舗さんもあります。
そして、売れるのにはもうひとつ理由があります。
店舗オーナーさんご自身もシニア層の方が多いので、商品を実際に試してくれます。従ってお客様への説明にもリアリティがあるのだと思います。売る側が納得しているから、買う側にも響きます。
【SLS】アイデアだけでなく、それを行動に移しカタチにしたことにも感心します。
【穴井】それは私たちが「営業」だからだと思います。常に外にキモチが向いているからです。
もちろん、社内を見渡せばこのような取り組みに反対意見もありました。
それは当然のことです。営業が動くだけと言っても現実には人件費も交通費も使います。経費はかかっています。
しかも1日に10件、20件回って成果がゼロということもあります。そうそう結果が出るわけではありません。そもそも、全くの異業種に対して「靴を売りませんか」と言っているのですから、結果が出なくて当たり前なのです。
しかし、動かなければ何も始まりません。それに仮に一店舗採用していただけると、そこから横の繋がりによって別のお店でも検討していただけることもあります。
【SLS】一通りのお話をお聞きすると、前述された「テレビ通販も流通対策の一環」というお話がよくわかります。
次回 : 「今後の展開と企業としての社会的使命」~「 労苦を共にした仲間とともに夢を実現する」