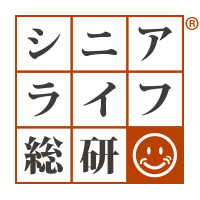第27回 アサヒシューズ株式会社
日本製への拘りと独自の販路開拓によって育成されたブランド「快歩主義」第3回
執行役員 / 営業・商品本部戦略ブランド販売部
快歩主義グループ ブランドマネージャー
穴井 政春氏
創業以来120年以上に渡って、高品質の靴を作り続けてきたアサヒシューズ株式会社。確かな技術と信頼の背景には、国内工場製造への深い拘りがありました。
そして、今シニア市場で話題の商品「快歩主義」は、健康・快適シューズ市場においてNo.1のブランド(※)に成長しています。(※2012年シューズポスト紙調べ)
今回は、この「快歩主義」ブランドの育成と販路拡大を含め、アサヒシューズのシニアマーケティングへの取り組みについて深くお話をお伺いします。
2018年5月取材

独自のプロモーション施策
【SLS】そんな自社工場で生産される「快歩主義」についてですが、高齢者の皆さんには「日本製」というキーワードは響きますか?
【穴井】響いていると思います。実際に「さすが日本製だけあって、モノが違う」というお声も多数頂いています。
【SLS】靴市場におけるシニアマーケットの特性を教えてください。
【穴井】まず大前提として、「快歩主義」の売上のうち多くを占めるのがリピーター需要ということです。
靴というのはそもそもリピート需要が大きい商品なのですが、「快歩主義」は一度お試しくださったお客様が繰り返し購入してくださることがとりわけ多い商品です。
【SLS】新規ユーザーの獲得については、どのように取り組んでいらっしゃいますか?
【穴井】これまでは新聞広告を中心に全国紙の15段広告や、時には5段広告も出稿してきました。しかしながら、期待するほどのレスポンスには至りませんでした。
特に地方についてはブロック紙や県紙などの地方紙が強く、全国紙ではなかなかリーチしないという印象を持ちました。
そこで考え方を変えて、2018年からテレビ通販によるダイレクトマーケティングを実施しています。

(穴井氏も出演する通販番組)
【SLS】ここまでの反響はどうですか?
【穴井】反応は良いと感じております。衛星放送を中心に29分の尺で放送していますが、毎日予測値以上の反応があります。
卸先の靴屋さんからは「メーカー直販すること」に対しお叱りをいただくことがあります。しかし私どもの真意は靴屋さんと競合することではありません。
この番組の主目的は、ブランドの持つストーリーや価値を伝達しながら快歩主義を知らない方にブランドの存在を知って頂く事です。通販はあくまで副次的な要素と考えています。
番組を通じてアサヒシューズの「快歩主義」をシニアの皆さんに知っていただき、その上で店舗に足を運んで頂きたいのです。
事実、靴は履いてみないと自分に合うかどうかわからない商品です。ご近所の靴屋さんで弊社商品と出会った際に、「テレビで見た商品だ」ということでお試し頂くきっかけになればと期待しております。
このことは営業マンがそれぞれの靴屋さんに足を運んでご説明しております。
【SLS】販売よりも流通対策としての意味合いが強いのですね。
【穴井】そうですね。快歩主義は一度お履き頂ければ必ずといっていいほどリピーターになって下さる方が多い商品です。一度お試し頂ける方を増やしたいという意味合いが強いですね。
また番組内では靴をご購入いただいた方へのノベルティとして「オリジナルの今治ハンカチタオル」をプレゼントしていますが、実はこのノベルティは店頭でもちゃんとご用意しております。
弊社としては何より小売店さんを大切にしたいという思いがありますので、店舗へ足を運んでくださったお客様が「プレゼントはテレビ通販だけなの?」という疑問や不満を持たれるのは本意ではありません。ですので「快歩主義」を取り扱うすべての小売店さんに同じノベルティを提供させていただいております。
多様なニーズへの対応がシニア攻略の鍵
【SLS】こうしたシニアマーケットへの取り組みが結実していると実感したのはいつ頃からですか?
【穴井】シニアマーケットにはまだまだ新しいニーズが存在するのだと気づいた辺りからです。
例えば同じ80歳の婦人を比較しても、20年前の80歳と今の80歳とでは全然違いますよね。
私自身もあと1年で60歳です。
自分が子どもの頃の印象では60歳と言ったらお爺ちゃんでしたが、実は私は今もハーレーを乗り回しています。
【SLS】ハーレーとは、すごい(笑)
【穴井】これが今60歳の実態です。もちろん一例ですが(笑)。
快歩主義で言うと、10年前はベージュ、黒、ワイン色などの定番商品しかありませんでした。
しかし、今のシニアは多様なニーズを持っています。それに呼応するため、今は定番以外にもたくさんのデザインをご用意しています。いわゆる「年寄り扱い」をしてはいけません。
こちらのショールームにはラインナップの一部を置いていますが、全体を見渡して頂くと、結構派手だと思いませんか(笑)

【SLS】そう思います。
【穴井】ちょっと派手なくらいが気持ちを高揚させてくれるし、その気持ちが歩いたり動いたりする原動力になります。
【SLS】リハビリ用の商品もデザイン性が高いですね。
【穴井】よくあるリハビリ対応の靴はデザイン性を考慮しない「上履き」的なものが多いのですが、私たちはリハビリ対応の靴であったとしてもデザインには拘っています。
とある介護施設で聞いた話をご紹介します。その施設の入所者さんたちが履く靴は全員が同じモノで間違いやすかった。そこに気づいた入所者の娘さんが、靴に名前を書く代わりにその方がお気に入りの着物の切れ端をミシンで靴に縫い付けたところ、とても喜んでくれた上に間違いも減ったそうです。
私どもはそのアイデアを即座にいただきまして、着物風の生地をワンポイントであしらった商品も作りました。
商品開発をしていても楽しいです。多少突飛なアイデアだったとしても、恐れずどんどんチャレンジしています。できれば他社にはない独自性のある商品をたくさん作りたいと思っています。
実際、社内会議で不評であったデザインでも、思い切って発売してみると、これが意外とよく売れることがあるのです。正直言って何がウケるかなどやってみないとわかりません。
もちろん定番商品自体は大事な存在です。そちらのラインナップはしっかりと維持しつつも、一方で色やカタチを少しずつ変えたアレンジ商品をラインナップとして増やしていく。そうすると2足目、3足目のプラス需要として売れていきます。だからこそ攻めていく姿勢は大事です。
この戦術は、コンバースさんの「オールスター」シリーズからヒントを得ています。
柱となる定番商品を持ちつつ、一方では常に攻めの商品ラインナップ開発を行っていく。これがシニアマーケティング攻略のポイントのひとつだと思います。
まだある、自社工場生産のメリット
【SLS】しかし、実際はこんなにたくさんのデザイン商品を作るのは大変なのではないですか?

(ハローキティともコラボレーションするなど、バリエーション豊富な快歩主義)
【穴井】こうした試みができるのも、自社工場があるからです。
仮に海外生産をしていたらこうはいきません。海外生産を行うためには、ロットと期間に制約が生まれます。
靴の世界でいえば、最低でも5,000足発注しなければ海外生産のコスト面のメリットは生まれず、しかも発売の半年前に発注するという条件が付きます。商品の売れ行きが見えない段階で、大量の発注を余儀なくされるわけで一種の賭けです。リスクも大きい。
仮に賭けに勝ちヒット商品を生んだとしても、そこからがまた大変です。
更なるヒットを生むために新型のモデルを大量に生産し販売する。そうすると当然前のモデルの中に売れ残りが発生し、それが安売りの対象になります。
最新でなくても安い方がいいという需要は必ず一定数はあります。そうすると売りたいはずの最新モデルが売れなくなり、ひいてはブランドの瓦解に繋がっていきます。
国内の自社工場であれば小さいロットで作り、売れなければすぐにやめればいいし、売れたら増産すればいい。ニーズに対し臨機応変に対応できるのが強みです。小回りが効くのです。
次回 : 「業種を超えた流通対策」~「異業種店舗で靴が売れる、その理由」